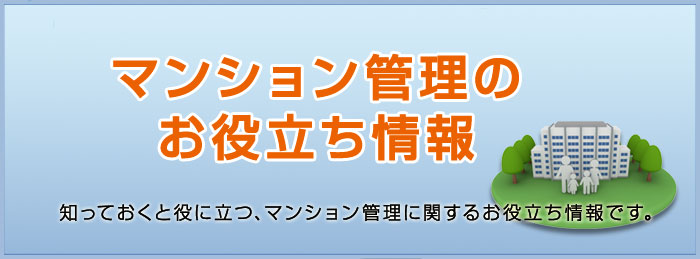区分所有法の改正について
今年の4月に区分所有法が改正され
マンションの管理組合に少なからず影響を与えます。
区分所有法とは、マンション等の共同建物における
所有関係・管理体制・居住ルールを法的に整備し
居住者間のトラブルを防ぎ円滑な管理を図るための法律のことです。
区分所有法はマンションの規模や築年数など一切関係なく
国内の全てのマンションに適用されます。
現在、弊社管理部門でもこの改正に向けて
情報の共有や対応のすり合わせを行っている最中です。
区分所有法は管理規約の定めにかかわらず優先されるため
個々のマンションで作成している管理規約も
法改正に則った内容に変えなければなりません。
マンション標準管理規約(※国土交通省が分譲マンションの管理組合向けに作成した、管理規約のひな形)も
それに則ったものに改正されており、内容もかなり変わっています。
今回はその中でも法律に抵触しないように
必ず変えなければならない条項について記載したいと思います。
必ず変えなければならない規定(カッコ内は標準管理規約の関係条項)
①特別決議についても総会の出席者による多数決に変更する(第47条)
②総会の定足数について、議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更する(第47条)
③「特別決議」を行う場合の総会の定足数を新たに規定する(第47条)
④バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を4分の3から3分の2に緩和する(第47条)
⑤新たなマンション再生手法である更新・売却・除却を行う場合の多数決要件を規定する(第47条)
⑥客観的な事由が認められる場合のマンション再生に係る決議の多数決要件を5分の4から4分の3に緩和する(第47条)
⑦総会招集時の通知事項として、全ての議案に「議案の要領」を示す(第43条)
⑧共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議について、多数決要件が緩和される場合は通知事項とする(第43条)
⑨緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「5日間」から「1週間」に変更する(第43条)
⑩共用部分等に関する損害賠償請求権等の行使について、旧区分所有者を含めて理事長による一元的な行使を可能にする(第24条の2)
⑪区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を行わないこととする規定を設ける(第24条の2)
⑫損害賠償金等の使途を制限する規定を設ける(第24条の2)
※この他にも改正を推奨する条項がありますが、今回は割愛します。
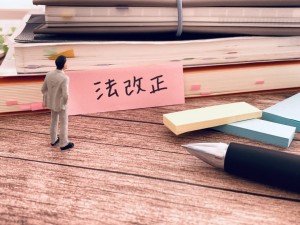
項目はたくさんあり、内容も複雑ですが
関係条項としては47条、43条、24条の3つです。
この3つは、各マンションの規約で
たとえどのような規定を設けていても、区分所有法が優先されます。
マンション標準管理規約は
国土交通省のホームページから確認できますので
理事会役員の方はご確認の上
規約改定について検討されることをお勧めします。
マンションの掲示板について
マンションの掲示板は、居住者への情報伝達に欠かせない重要なツールです。
しかしその運用を誤ると、トラブルの原因にもなりかねません。
適切な管理と運用のために押さえておくべき注意点について解説します。
1.掲示内容の管理
掲示板に掲載できる内容は
基本的に管理組合からの公式なお知らせに限定されるべきです。
具体的には、総会や理事会の開催案内、工事や点検の予定
防災・防犯に関する情報、管理規約で定められた事項などが該当します。
これらは居住者全体の利益に関わる重要な情報であり
確実に伝達する必要があります。
一方で、掲示板に掲示すべきでない内容も明確にしておく必要があります。
個人の私的な売買や譲渡の情報、政治的・宗教的な宣伝
特定の居住者を批判する内容、営利目的の広告などは
原則として掲示できません。
ただし、ボランティアイベントのチラシや自治体の広報など
管理組合が公益性を認めた広告については
例外的に掲示を許可する場合もあります。
こうした基準を管理規約や使用細則等で明文化しておいてもいいでしょう。
2.掲示のルール設定
掲示物を掲示板に貼り出す際には
原則として理事会または管理会社の事前承認を得ることが重要です。
これにより、不適切な内容の掲示を未然に防ぐことができます。
ただし、災害時の緊急連絡など
緊急性の高い情報については事後承認とするなど
柔軟な対応基準を設けておくことも必要です。
また、すべての掲示物には作成者や掲示責任者を明記しておくべきです。
掲示期間の管理も重要なポイントです。各掲示物には掲示日を明記し
一定の期間が過ぎたものは速やかに撤去する体制を整えましょう。
古い情報が放置されたままになっていると
掲示板全体の信頼性が低下し
重要な新しい情報が見落とされる原因にもなります。
3.法的注意点への配慮
掲示板の運用においては、法的なリスクにも十分注意を払う必要があります。
特に個人情報の取り扱いには慎重であるべきです。
居住者の氏名や部屋番号などの個人情報は
必要最小限にとどめることが原則です。
例えば、管理費の滞納者名を掲示板に公表するような行為は
プライバシーの侵害や名誉毀損にあたる可能性があり、避けるべきです。
また、特定の居住者に関する苦情や批判的な内容を掲示することは
名誉毀損のリスクを伴います。
仮に事実であったとしても、公然と掲示することで
法的責任を問われる可能性があります。
こうした問題は、適切なルートで個別に対応すべきであり
掲示板を使うべきではありません。

4.効果的な運用方法
掲示板を効果的に活用するためには、レイアウトにも工夫が必要です。
緊急性の高い情報、日常的なお知らせ、イベント情報などを
エリアごとに分けて配置することで
居住者が必要な情報を見つけやすくなります。
また、文字サイズは高齢者でも読みやすい大きさにし
カラー用紙を活用するなどして視認性を高める工夫も有効です。
近年では、デジタル技術との併用も効果的です。
掲示板の情報にQRコードを付けて
詳細情報にアクセスできるようにしたり
メール配信やマンション管理アプリと併用したりすることで
より確実な情報伝達が可能になります。
特に若い世代は掲示板を見ない傾向がありますので
複数の伝達手段を用意しておくことが重要です。
5.トラブル防止策
無断で掲示物を貼り出す居住者への対応も考えておく必要があります。
無断掲示を発見した場合は、速やかに撤去し
全居住者に対して掲示ルールを改めて周知することが大切です。
繰り返し違反が続く場合は
管理規約に基づいた罰則の適用も検討すべきでしょう。
また、掲示板をめぐって居住者間の意見対立が生じることもあります。
特定の問題について賛成・反対の意見を
掲示板上で応酬するような事態は避けなければなりません。
掲示板は一方向の情報伝達の場であり
議論の場ではないという原則を徹底し
意見や要望は総会や理事会など
適切なルートで受け付けるようにしましょう。
6.継続的な管理の重要性
掲示板の適切な管理には、定期的なチェックが欠かせません。
週に一度程度は掲示物のチェックを行い、状態を確認しましょう。
破れや汚損があれば貼り直し、整理整頓された状態を維持することで
掲示板の信頼性と機能性を保つことができます。
さらに、掲示した内容の記録を保管しておくことも重要です。
掲示物のコピーを日付とともに保管しておけば
後日トラブルが発生した際の証拠資料となります。
また、情報伝達の履歴として、管理組合の活動記録にもなります。
最後に
マンションの掲示板は「マンションの顔」とも言える場所であり
適切に運用すれば居住者への確実な情報伝達と
良好なコミュニティ形成に大きく貢献します。
一方で、ルールが不明確なまま運用すると
プライバシー侵害や名誉毀損などの法的リスクを招いたり
居住者間のトラブルの原因になったりする可能性もあります。
管理組合は掲示板に関する明確なルールを定め
それを居住者全体で共有することが重要です。
そして、時代の変化や居住者のニーズに合わせて
定期的にルールや運用方法を見直していく姿勢も求められます。
適切な掲示板管理を通じて
より住みやすいマンションづくりを目指しましょう。
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
近藤リフレサービス㈱は、新しい仲間を募集中です。
あなたの力で、快適な暮らしを支えませんか?
詳しくはこちら https://www.refremk.com/recruit/
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
マンションにおける個人情報取り扱いの注意点
マンション管理組合や管理会社が取り扱う個人情報は
適切に管理しなければ重大なトラブルにつながります。
近年、個人情報保護法の意識が高まる中
マンション管理の現場でも慎重な対応が求められています。
以前もブログで個人情報について書かせていただきましたが
今回は取り扱いの注意点について深掘りしていきます。
1. マンションで扱う個人情報の範囲
マンション管理において取り扱う個人情報は多岐にわたります。
区分所有者や居住者の氏名、住所、連絡先はもちろん
家族構成や年齢、管理費・修繕積立金の滞納情報なども該当します。
さらに、駐車場や駐輪場の利用状況、ペット飼育状況
防犯カメラの映像記録なども個人情報として扱われます。
これらはすべて個人情報保護法の対象となるため
取り扱いには十分な注意が必要です。
2. 管理組合が注意すべきポイント
(取得時の注意点)
個人情報を取得する際には、まずその利用目的を明確に伝えることが重要です。
「マンション管理のため」といった漠然とした説明ではなく
「緊急連絡用」「管理費請求のため」など具体的な目的を示す必要があります。
また、必要最小限の原則に基づき
管理に本当に必要な情報のみを収集するよう心がけましょう。
(保管・管理の注意点)
収集した個人情報は適切に保管しなければなりません。
紙の書類は鍵付きキャビネットに保管し
USBメモリやパソコンで管理する場合はパスワードの設定など
第三者が閲覧できないような工夫が必要です。
また、閲覧できる人は管理会社と理事会メンバーなど必要最小限に限定し
原則として個人情報を外部に持ち出さないルールを徹底することが大切です。
理事が自宅に書類を持ち帰る際は、紛失等しないよう注意しましょう。
(使用時の注意点)
個人情報は取得した目的以外での使用が禁止されています。
例えば、管理費徴収のために取得した連絡先を
理事が個人的な勧誘活動に使用することは違法です。
また、理事会の議事録に個人名を記載する際は慎重に判断し
掲示板に滞納者名などを公開することは原則として避けるべきです。
個人を特定できる情報の公開は
プライバシー侵害や名誉毀損につながる可能性があります。

3. よくある問題事例
実際にマンション管理の現場では
個人情報の取り扱いに関する問題が発生しています。
例えば、総会で全戸の連絡先一覧を無断で配布してしまったケースがあります。
これはプライバシー侵害となり、訴訟リスクを伴います。
また、掲示板に「○○号室の△△様、管理費が未納です」と
掲示してしまった事例もあります。
これは名誉毀損に該当する可能性があります。
さらに、理事が名簿を使って個人的な勧誘活動を行ったケースも報告されています。
これは明らかな目的外使用であり、違法行為です。
4. 防犯カメラの取り扱い
防犯カメラの映像も重要な個人情報です。
設置する際には、防犯目的であることを明確にし
撮影範囲は共用部分のみに限定します。
各住戸の玄関ドア内部が映らないよう配慮が必要です。
また、「防犯カメラ作動中」といった表示を設置し
居住者に周知することも大切です。
録画された映像の管理も慎重に行う必要があります。
閲覧できる人は管理会社や理事長、理事長が認めた者など
限定されたメンバーのみとします。
警察からの要請など正当な理由がある場合を除き
第三者への提供は避けるべきです。
居住者から「隣人とのトラブルで証拠が欲しい」と言われても
安易に映像を提供することは個人情報保護の観点から避けた方がいいです。
5. マンション特有の配慮事項
マンションという集合住宅ならではの配慮も必要です。
住民間のトラブルが発生した際
「隣人の連絡先を教えてほしい」と言われることがありますが
原則として個人情報を第三者に開示することはできません。
苦情対応で相手の情報を開示する場合も
匿名での対応を基本とするべきです。
最後に
マンション管理における個人情報保護は、法的義務であると同時に
居住者との信頼関係を築く上で欠かせない要素です。
必要な情報のみを収集し、適切に保管・管理し、目的外使用をせず
不要になったら確実に廃棄するという基本原則を守ることが重要です。
小規模なマンションであっても個人情報保護法は適用されます。
「知らなかった」では済まされないため
管理会社と連携して適切な管理体制を構築しましょう。
不明点がある場合は
管理会社や個人情報保護の専門家に相談することをお勧めします。
適切な個人情報管理は
安心して暮らせるマンションづくりの基盤となります。
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
近藤リフレサービス㈱は、新しい仲間を募集中です。
あなたの力で、快適な暮らしを支えませんか?
詳しくはこちら https://www.refremk.com/recruit/
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
ランニングコストを見直して支出削減
近年、物価や人件費の急激な高騰により
マンションを維持管理していくためのランニングコストが上昇し
今までの管理費では賄えない事態となっている管理組合が増えてきています。
電気料の値上がりや、火災保険料の価格改定だけでなく
日常的な修繕費や備品消耗品などの物品の価格も軒並み値上がっており
どこというより全ての費用が底上げされている状況です。
清掃や点検を行っている業者から
人件費や材料費、燃料費、交通運搬費等の高騰を理由に
やむを得ず値上げの申し出があった管理組合も
少なくないのではないでしょうか。
そもそも管理費とは
共用部分の電気料金や水道代、管理会社の委託料など
以下のような通常の管理に必要な経費のことをいいます。
・電気料金・水道代
・管理員の人件費
・共用設備の保守点検費
・清掃費及びごみ処理費
・機械警備を含む警備費
・備品消耗品費、通信費
・共用部分の火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
・経常的な修繕費
・清掃費及びごみ処理費
・植栽の維持管理費
・委託業務費
・専門的知識を有する者の活用のための費用
・公租公課
・その他の運用費
これらの経費は日々の生活に深く関係しているものが多く
コストの削減は容易ではありませんが
保険会社や保険内容の見直し
マンションの火災保険は、近年の自然災害の増加や
築年数の経過したマンションでの漏水事故の増加により
度々料率が改定されており、値上がりが顕著です。
但し、保険会社によって提示される保険料は様々ですので
現在の保険契約がまもなく終了となる段階で
別の保険会社に相見積をとってみるのも良いと思います。
それでも高額であれば
建物評価額や付保割合を下げて保険料を下げるといった方法もありますが
保険事故で支払われる限度額を下げるリスクが伴いますので、ご承知おきください。
電子ブレーカーの導入
共用部分のブレーカーを電子ブレーカーというものに交換すると
いままでの「負荷設備契約」から「主開閉器契約」という
別の電力契約に変更ができます。
「主開閉器契約」にすると
電気の基本料金を削減することが出来
特に機械式駐車場やエレベーターなどが設置されているマンションに
削減効果が期待できます。
LED照明器具への交換
LEDは少ない電力で従来の照明と同等の明るさを維持します。
共用部分は照明が多いので、より電力削減効果が期待できます。
また、2027年末までに一般照明用蛍光ランプの
製造・輸出入が禁止となるようですので
まだ蛍光灯のマンションは、LED器具への交換をお勧めします。
清掃・保守点検の見直し
館内清掃や排水管清掃などの清掃業者や
消防設備点検やエレベーター点検などの各種点検業者を
より安価な業者に変える方法もあります。
しかしながら、変えることにより
作業の質が落ちてしまうリスクもありますので
業者は変えず、清掃内容や点検内容だけを見直しても良いと思います。
例えば、排水管清掃の日数を今までの2日間から1日間に変更したり
エレベーターの出張点検の回数を減らしたりして
費用を削減してもらう等の方法が考えられます。
管理委託契約の見直し
上記の見直しと同じですが
管理会社に委託している業務の中で削減できるものがあれば
なくしてもらう方法もあります。
例えば、管理員をなくしたり
会計業務のみを依頼して、その他の理事会運営は役員が担っていったり等の
削減方法が考えられます。
管理費の大部分が管理委託費になっている管理組合も多いと思いますので
費用の削減効果は期待できますが
その分不便にはなりますので
本当になくしても良いのか、穴埋めはできるのか
よく検討してから決めましょう。
ランニングコストの削減にはいろいろな方法がありますが
全てに共通しているのは
それなりの手間と時間がかかることです。
かといって、物価の高騰はまだ収まる気配がありませんので
うかうかもしていられません。
理事会役員には頭の痛い話ですが
特に管理費が赤字会計の管理組合は
なるべく早く手を打ち、黒字化を目指しましょう。
排水管清掃の実施率を上げるために
マンションの排水管清掃は
排水管の詰まりや悪臭などのトラブルを防止するために
定期的におこなうことが望ましく
年に1回程度実施しているマンションが多いと思います。
排水管清掃とは、住戸内の台所・洗面所・風呂場・洗濯機の排水を流すための管を
高圧洗浄ポンプを用いて水の力で
管内の汚れをそぎ落としていく洗浄作業になります。
なるべく下の階から清掃をはじめることにより
管内の清掃作業中に下部が詰まって
上から汚水が溢れ出るといった事故を防ぎます。
余談ですが、近年ドラム式洗濯機を使用する方が増えてきましたが
ドラム式は本体サイズが大きいため
設置スペースの問題で洗濯機の下に排水口が隠れてしまい
洗濯機下の排水口からの清掃ができないケースが増加しています。
ドラム式洗濯機は重量があるため自力で移動させることは困難です。
清掃業者によっては一時的に洗濯機を持ち上げるなどの対処をする場合もありますが
洗濯機の故障や壁面の破損の原因になるため、あまり一般的ではありません。
こういった場合には、 洗濯機の下部にスペースを空けるための
嵩上げ台なども市販されているため
設置を検討してみるのも良いかと思います。
排水管は各住戸の床下の横引き管から共用の竪管につながっているため
部分的に清掃をおこなっても効果が薄いので
できるだけ多くの住戸で清掃をおこなうことが大切で
住戸内への立ち入りが必須となる作業です。
しかしながら、実際には協力を得られない居住者も多く
実施率が上がらない問題が起こっているマンションも多いのではないでしょうか。

実施率の低いマンションの傾向として
「共働き夫婦の多いマンション」や「賃貸がメインのマンション」で
より実施率が低い傾向にあります。
前者は仕事などの都合により在宅できない
後者はあくまでの借りているだけの部屋なので維持管理に理解が浅い
といった理由が聞かれます。
管理会社も各部屋の鍵を預かることは原則としてありませんので
代わりに実施することは出来ません。
こうした問題を解決することは容易ではありませんが
実施率を高める方法として、以下のような案があります。
①清掃実施日を増やす
排水管清掃の実施日を増やすことによって、居住者の選択肢が増え
仕事などの都合により実施できない方を減らすことが期待出来ます。
実施日を増やす場合、事前に居住者へ
どの曜日が良いかアンケートを行うことにより
期待できる効果が目に見えて判るので
検討してみるのもいいでしょう。
但し、実施日を増やすことにより
当然ながら業者手配の費用がより多く掛かりますので
事前に費用対効果を検討してから増やすのが良いでしょう。
②排水管清掃の重要性を記載した書面を配布する
排水管清掃を「実施することにより得られる効果」(悪臭の軽減など)
「実施しないことによるリスク」(管の詰まりによる排水の溢れ
他の住戸への漏水事故など)を記載して
実施を促す書面を配布してみるのも一つの手です。
居住者の中には、排水管清掃の重要性が
あまり判らない方もいるかもしれませんので
理解を深めてもらうことにより、実施に前向きになってもらいます。
全ての方に効果があるわけではありませんが
一部の方には実施するきっかけになるかもしれません
マンションの排水管清掃は法定業務ではありませんが
汚れが蓄積してからでは深刻な問題が発生することもあるため
定期的に清掃が必要です。
また、前述したとおり居住者の在宅が必ず必要になります。
そのため、居住者の都合で
毎回同じ部屋で排水管清掃を実施できない事例も多いのが実態です。
しかしながら、長期間清掃を実施しないと、排水不良が生じて
場合によっては排水が漏れて下階への漏水事故につながる恐れもあるため
先程提示した案のように
できるだけ実施率を高めるための工夫が必要となります。