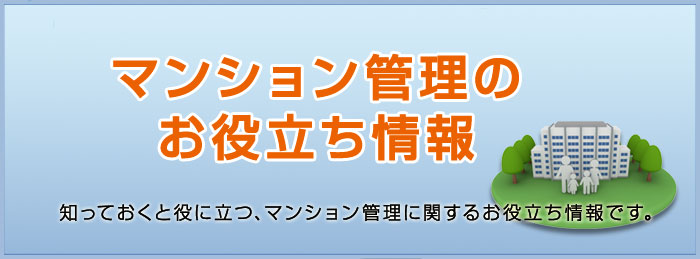機械式駐車場の維持管理
地方都市や郊外のマンションでなくてはならないものとして駐車場があげられますが
マンションによって色々なタイプの駐車場が設けられています。
主な駐車場のタイプをあげますと
平面式駐車場・・・一番オーソドックスでシンプルな駐車場。
敷地の空きスペースなどを利用して、白線を引いて区画を設け
その区画ごとに駐車します。
広い敷地を必要としますので
地方都市のマンションや郊外のマンションなどでよく利用されています。
マンションの敷地の路面に直接駐車しますので
メンテナンスの費用はほとんどかかりません。
(アスファルトや白線の引き直し位でしょうか)
立体自走式駐車場・・・平面式駐車場をさらに有効活用し
2層3段、3層4段というようにフラットな駐車場と
車が上下階に出入りするスロープなどを組み合わせた駐車場です。
平面式駐車場と同じように平面区画に駐車ができますが
より多くの台数の車を収納することが可能で
また機械式駐車場に比べて設備のメンテナンス費用が安くなる傾向があります。
大規模なマンションに設置されている方式です。
機械式駐車場・・・狭い空間を有効利用することを目的として普及してきた形態です。
2段パレット、3段パレットといったように
パレット(車が乗る台)が機械操作により上下あるいは左右に移動することにより
車の出し入れを行います。
操作盤を利用して自身の車の入っているパレットを呼び出して
車の出し入れを行います。
この中でも、機械式駐車場は狭い空間で多くの車が停められるため
「容積率いっぱいにマンションを建てたい」
「建築の条件で戸数分の駐車場を設ける必要がある」
といった理由により広く普及されてきましたが
大なり小なりいろいろなデメリットがあります。

維持管理費用が高額
機械式駐車場には多くの部品が組み込まれています。
パレット、制御盤、モーター、チェーン、ベアリングなどなど・・・
当然ながらその部品も少しずつ劣化していきます。
その部品交換費用がかなり高額です。
例として、今から5年程前に
あるマンションの6パレット、計16台駐車可能な機械式駐車場で
モーターとその他部品(リミットスイッチ、落下防止ソレノイド)を交換したところ
およそ350万円程の費用が掛かりました。
もちろん、部品はそれだけではないので
他の部品も交換時期が来たら順次交換する必要があります。
また、部品の交換以外にも保守点検の費用がかかります。
上記部品交換を行ったマンションでは
年間22万円程の点検費用が発生しています。
もっとも、法定点検ではない為
必ずしも実施しなければならないことはありませんが
事故防止の観点からも
点検による出費はやむを得ないところではあります。
高さ制限がある
分譲マンションで一般的となっている
2段、3段ピット式の機械式駐車場の場合には
最上段に停めている車には高さ制限はありませんが
中段以降には高さ制限があります。
築年が経過したマンションですと、中段以降の高さ制限が厳しく
今時の軽自動車でも入庫出来ないことが多いです。
この高さ制限のために空き駐車場が増え
駐車場収入が思うように入らないマンションも多いです。
入出庫するまで時間がかかる
駐車位置によっては、車を実際に入出庫させるまでに
数十秒から数分の時間を必要とすることから
利用者が不満を抱くケースも多いようです。
以上でもっとも頭を悩ませるデメリットとすれば
高額な維持管理費用ではないでしょうか。
対策として駐車場使用料の見直しや
マンション外の方に貸す「外部貸し」などで
収入を増やす方法があげられますが
値上げには限界もありますし
「外部貸し」は法人税を納めなければならない場合もありますので
簡単には解決しません。
ひとつの解決策として
弊社の管理マンションで機械式駐車場の埋め戻しを行ったところが幾つかあります。
機械を全て撤去して土や砂利などで空間を埋め、コンクリートを敷き
平面式駐車場にしました。
工事費用は掛かりましたが
コンクリートなので今後維持管理費用はかかりません。
現在機械式駐車場を利用されている方の理解を得ることは容易ではありませんが
維持管理費用でお悩みでしたら
埋め戻しも一つの案として考えてみてはいかがでしょうか。
個人賠償責任保険について
マンションのオーナーとなった際に
ほとんどの方が火災保険の加入を検討されるかと思いますが
火災保険と併せて付保しておきたい保険が
「個人賠償責任保険」です。
「個人賠償責任保険」とは
自動車事故以外の日常生活の事故により
他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい
法律上の損害賠償責任を負った場合に補償が受けられるものですが
この保険、マンションにはつきものである漏水事故にも対応しています。
マンションで漏水事故が発生した場合
被害に遭われた下階のお部屋を原状回復する必要がありますが
この費用は漏水発生元である上階オーナー(または居住者)が
全額負担しなければなりません。
その際、「個人賠償責任保険」を付保していれば
この費用の一部または全額が補償の対象となり
上階オーナーの負担軽減が見込めます。
下階の原状回復費用は被害の状況によってまちまちですが
なかにはかなり高額な請求となるケースもあります。
例として、私が直近でご対応させていただいた
漏水事故3件の下階の原状回復費用をあげますと
・Aマンション 663,300円(天井ボード交換、クロス貼替、フローリング貼替)
・Bマンション 316,250円(天井ボード交換、クロス貼替、照明器具交換)
・Cマンション 1,370,600円(天井・壁ボード交換、クロス貼替、フローリング貼替)
※いずれも税込み
個人でお支払いするにはかなりの負担ではないでしょうか。
管理組合でも共用部分で付保している
「マンション総合保険」の特約としてこの保険が付いていることがあり
その場合、マンション内の漏水事故であれば
どのお部屋でも保険申請が可能ですが
近年の保険料値上げにより
この保険を付保しない管理組合も増えてきています。
ご自身のマンションでこの保険に加入しているか
一度ご確認をお勧めします。
もし管理組合でこの保険を付保していない場合は
ご自身の火災保険に「個人賠償責任特約」が
付保されているか確認してみてください。
(保険会社によっては「日常生活賠償責任特約」だったりと名称は様々です)
火災保険以外でも
例えば自動車(じどうしゃ)保険に付いているケースもあります。
自転車(じてんしゃ)保険でしたら
それだけで「個人賠償責任保険」と同じ補償が受けられますので
新たに付保する必要はありません。
いずれの保険にもない場合は付保を検討してみてください。
月額にすると数百円程度の負担で付保出来るところがほとんどですので
もしもの備えとしては高額ではないと思います。
漏水事故はいつ発生するかわかりません。
突然高額な費用を請求をされる前に、備えておきましょう。
管理組合としての個人情報保護
管理会社に業務委託しているマンションでは
一般的にマンションの居住者の個人情報は
「個人情報保護法」に基づいて管理会社が管理しています。
しかし、自主管理のマンションだったり
管理会社に委託していても災害時に備えて居住者名簿を理事会が保有する等
管理組合が管理することもあるでしょう。
この場合には、個人情報やプライバシーの保護を厳守して
第三者に情報が流出しないよう取り扱いに十分注意したいものです。

「個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)」は
個人の権利利益を保護することを目的として定められた法律で
個人を識別できる情報を多く取得する立場にある事業者を管理するための法律です。
2017年5月の法改正により
「取り扱う個人情報の数が5000人以下である事業者を法規制の対象外」
としていた制度が廃止され
マンションの管理組合も例外なく個人情報保護法の対象となりました。
管理組合が扱う個人情報には、一般的に
居住者の「氏名」「住所」「連絡先」等が記載された居住者名簿や
滞納者の情報等がありますので
理事会で保有する際には第三者に情報が漏れないよう注意してください。
また、プライバシー保護の観点でいえば
理事会活動のなかで、理事はマンションの居住者の職業や
交友関係などを知る機会があると思います。
居住者のプライベートな情報を議事録に記載して
それを全戸に配布したり、掲示したりすることは
個人のプライバシーを侵害するおそれがありますのでやめましょう。
理事会の業務は、あくまでもマンション共用部分の管理を目的としたものであり
居住者のプライベートについては基本関わるべきことではありません。
しかしながら、理事会の業務の中で
自然と知りえる情報もあると思います。
「個人情報保護法」の遵守は当然のことですが
居住者のプライバシーに関する事柄についても
その取扱については十分に配慮をおこなうことが重要です。
会議の議事録について
管理組合の会議の議事録には
決議の結果や参加者から出された意見などが記録されており
現在や過去のマンションの状況を知る上での大事なツールとなります。
マンションで行われる会議には、主に総会と理事会がありますが
組合員全体を出席対象とした総会については
区分所有法第42条第1項の規定により、議事録の作成が義務付けられています。
総会の議事録は、原則として議長を務める理事長が作成しますが
選任された理事などが議事録の作成をおこなう場合もあります。
但し、管理会社に管理を委託している場合
管理会社の担当者(フロントマン)が理事会に同席し
議事録の素案を作成していることが多いのが実状です。
議事録の作成には手間と時間がかかるため
管理会社に作成してもらうのは結構なことですが
作成者はあくまでも議長(理事長)であるため
議長は管理会社の作成した素案の内容をよく確認のうえで
署名、押印することが大切です。
議事録の書き方に決まりはなく
議事の内容をすべて記載する必要はありませんが
日時・出席者数・議案・決議結果などの要点を
正確に記載する必要はあります。
また、そのマンションごとにある程度書式を決めて作成したほうが
読む側(組合員)はより読みやすくなります。
議事録を全戸に配付するかどうかは
管理規約等に定められている場合のほか
各管理組合の慣例等により異なります。
弊社でも以前は議事録のコピーを全戸に配布しておりましたが
ペーパーレス化の観点から、紙での配布をなるべく控え
管理組合専用のポータルサイト上で議事録を確認頂くよう努めております。
近年は、時間がかかる、家の用事を優先したい等の理由で
総会の出席を委任する人が増えているように思えます。
いくら時間をかけて議論をかさねても
組合員に結果を伝え共有しなければトラブルにも繋がるため
議事録の作成・公開は大切です。
できる限り多くの組合員の目に留まる方法で
議事録を公開することが望ましいでしょう。
エレベーター点検について
多くのマンションに設置されている「エレベーター」
快適に生活する上でなくてはならない設備ですが
精密な機器が沢山組み込まれているため
安心・安全に利用するために点検は欠かせません。
エレベーターは建築基準法12条3項の規定により
年に1回の法定点検が義務付けられています。
管理者(主に理事長)は基準に則って「定期検査」をおこない
検査結果を特定行政庁に報告する必要があります。
過去にエレベーターの誤作動によるいたましい事故も起きていますので
誰でも安心・安全に利用するために
管理者は必ず法定点検を実施しなければなりません。
但し、実際には年に1回義務付けられている法定点検だけではなく
1か月や3ヶ月に1回の頻度で点検業者に点検を依頼している管理組合がほとんどであり
それだけ安全面が重要視されています。

エレベーター点検には
「POG契約」と「フルメンテナンス契約」の2種類の契約があります。
「POG 契約」とは、「パーツ・オイル・グリス」の略で
定期的な機器・装置の点検を行うことに加え
電球・ヒューズ・リード線などの消耗品の交換や、オイル・グリス等の補充のみを行い
劣化した部品の取替えや修理等の費用を含まない契約のことをいい
比較的安価です。
「フルメンテナンス契約」とは、上記「POG契約」の内容に加え
点検結果に基づき、劣化した部品の取替えや修理等も行う契約のことをいい
費用は比較的高額です。
「フルメンテナンス契約」は未来の部品交換費用を
毎月少しずつ支払っている感覚に近いです。
そのため、設置から期間が経過したエレベーターでは交換部品が増えてしまい
点検業者の利益が見込めないため、契約を断られることが多いです。
「POG契約」でも点検時に交換が必要と判断された部品に関しては
点検業者から後日交換の提案と見積が提出されますので、その点はご安心ください。
どちらの契約が良いということはありませんが
通常、点検費用は管理費会計、部品交換費用は修繕積立金会計で賄われていると思いますので
管理組合の懐事情をみて、契約を検討していきましょう。