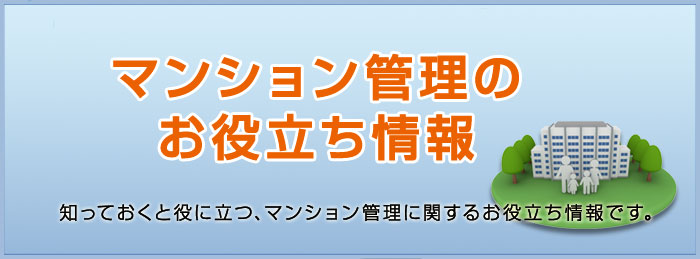マンション保険の見直し
マンション保険の見直し
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マンション共用部は全区分所有者が共同で所有する部分になっており、その
維持管理は管理組合です。
マンション標準管理規約でも、共用部分の火災保険その他の損害保険に関する
業務は「管理組合の業務」としており、これらに従い、多くのマンションの
管理規約には、共用部分の火災保険等の損害保険を契約することは管理組合の
業務と定めています。
マンションでは、一度火災や爆発などの事故が発生すると、被害はその住戸
だけではなく他の住戸や共用部分にまで広がり現状復帰に多額の費用を要します。
このような場合の対策として、管理組合で掛けるマンションの共用部分を守る
損害保険がありますが、現在の保険内容について考えてみましょう。
契約者名は?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
全ての契約は、管理組合・理事長名ですか?
理事長が決定する間、管理会社名で加入する場合があります。
すぐに変更しましょう。
火災保険は?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
保険証券に記載されている面積・構造等に誤りはありませんか?
施工前の数値が記載されていることがあります。すぐに変更しましょう。
施設賠償保険は?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
算出根拠の面積に、必要な箇所が含まれていますか?
マンションの敷地内にあるマンションの棟以外の共用設備が含まれていない
ケースもあります。確認しましょう。
※保険会社によって火災保険商品が異なることがある点はご留意ください。
※マンションの設備によって異なりますのでご注意ください。
地震保険について
地震保険とは
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マンションの地震保険には、
「共用部分の地震保険」と「専有部分の地震保険」の、
2種類の保険があり、共用部分は建物となり専有部分は家財となります。
地震・噴火または、これらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または
流失による建物の損害、地震等により延焼・拡大したことによる損害を受けた
場合を補償する保険です。
地震保険は単独で契約することができないため、必ず火災保険に付帯して契約します。
地震保険の対象
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
住居として使用されている建物(居住用建物)の共用部分
住居部分のない専有部分およびその共用部分の共有持分は地震保険の対象と
なりません。
地震保険の対象外
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
共用部分の損害認定が基礎や柱などの「主要構造部」を中心としているため、
水道管やガス管などのライフラインや外壁、エレベーターなどの損害は認定の
対象外となります。
地震保険の保険料
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
お住まいの都道府県や建物の構造によって決まっているようです。
また、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
※主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の
50%以上となった場合または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物
の延床面積の70%以上となったときは、マンション共用部分の地震保険金額の
100%(時価額が限度)が支払われる保険金となります。
※保険会社によって火災保険商品が異なることがある点はご留意ください。
主な特約の補償内容
水濡れ原因調査費用特約
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
漏水が発生した場合、まずどこから水が漏れているか確認する必要があります。
調査費用は漏水の原因が専有部にあれば専有部の管理者が、原因が共用部に
あれば共用部分を管理する管理組合が負担するのが一般的ですが、原因箇所が
解らなければどちらが調査費用を負担するかトラブルになる場合もあります。
このような場合、「水濡れ原因調査費用」が支払われますので、漏水事故が
発生した時の原因調査費用に掛かるトラブルを防止することができます。
また、給排水管の劣化や、排水管の詰まり、お風呂場から水があふれた場合や、
洗濯機のホースが抜けたことに起因する場合などがあります。
このような原因に起因する水漏れの場合、上階の方は下階の方へ損害賠償の
義務を負うこととなりますが、上階の方に賠償するお金を支払うことができず
下階への賠償や復旧工事が行えなかった場合にはトラブルに発生することも
考えられるのです。
1回の事故につき、限度額があります。
個人賠償責任補償特約
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
保険で法律上の損害賠償責任に対応することによりトラブルを防止すること
ができます。
個人賠償責任補償特約は専有部分の火災保険にプラスして契約することも可能
ですが、管理組合が一括して個人賠償責任補償特約(包括契約用)を契約する
ことにより、どこの部屋で問題が発生しても対応できるようにすることができ
ます。
居住者などが、専有部分の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または日常
生活に起因する偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担される場合に
補償されます。
事故状況等により賠償責任が発生しない場合があります。
共用部分の設備特約
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
建物の共用部分に起因する偶然な事故等によって、他人の生命または身体を
害したり、他人の財物に損害を与え法律上の損害責任を負った場合です。
共用の空調設備、電気設備等の対象設備が建物において、稼働可能な状態に
ある場合、電気的、機械的な事故によってその対象設備に損害が発生した場合
となります。
1回の事故につき、限度額があります。
水災害特約
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等による
マンション共用部分の損害を補償します。
建物が床上浸水又は地盤面より45センチを超える浸水を被った場合。
また、保険対象である建物の共用部分にその再調達価格の30%以上の損害が
発生した場合も保証されます。
※保険会社によって火災保険商品が異なることがある点はご留意ください。
不動産仲介業者の方へ 管理に係る重要事項調査報告書の発行について
不動産仲介業者の方へ
管理に係る重要事項調査報告書の発行について
当社は、宅地建物取引業法第35条第1項第5号の2及び同法施行規則第16条の2及び第16条の4の3等の定めによるマンション取引等に係る重要事項調査依頼につきましては、下記の通り対応をさせていただきますので、よろしくお願い致します。
[依頼方法]
重要事項調査依頼書に必要事項をご記入の上、FAX送信していただき、受付後「管理に係る重要事項調査請書」をFAX送信いたします。振込先・振込金額は、管理に係る重要事項調査請書に記載されています。
着金確認後作成に入りますので、調査手数料の振込控のFAX送信をお願い致します。
[調査手数料一覧]
重要事項調査報告書 5,500円(税込)
管理規約・使用細則 4,400円(税込)
長期修繕計画書 3,300円(税込)
※建物により無い場合があります
次の内容をご確認いただき、重要事項調査依頼書をダウンロードしてください。
[同意事項]
本調査は、管理委託契約第14条に基づいて、売主である区分所有者(法定代理人を含む)及び管理組合が保有する規約、総会資料(議案・議事録)等で、弊社が把握している内容を開示するものです。本調査に含まれる項目であっても、弊社が把握していない内容については、調査結果に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。また、弊社が把握している内容以外の事項より生じるいかなる損害についても、弊社はその責を負いかねます。
[注意事項]
(1) 総会議案書等について
調査対象物件の総会議案書・総会議事録については、原則売主(当該住戸の現区分所有者)の方から引き継ぎもしくは管理組合所定の手続きによる閲覧をお願い致します。なお、守秘義務に基づき、当社から開示及び郵送等はできませんので、予めご了承下さい。
(2) その他
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、第三者によるデータの改ざん等があった場合、さらにデータの伝送等によって障害が生じた場合に関しましては、当社は一切の責任を負うものではありませんので、予めご了承下さい。
[問合せ先]
〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7
近藤リフレサービス株式会社
TEL049-256-8500 FAX049-256-8780
[受付時間]
月曜日~金曜日 9:00~17:00
重要事項調査依頼書をダウンロード
マンション保険の特徴
マンションの共用部分の保険とは?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マンションには専有部分と共用部分があります。専有部分に自分で保険をかける
ことはもちろんですが、共用部分の場合、管理組合で一括して保険をかける
ケースが多くなります。
管理組合では、建物・設備の共用部分の損害を補償する「物」保険と、管理組合が
法律上の賠償責任(例えば、共用部分の給排水管から水漏れがおこり、専有部分に
損害を及ぼした。
外壁が剥がれ落ち、通行人にケガをさせた等)を負った場合に対応できる、
「賠償責任」保険にはいっておくと良いでしょう。
万一、事故が発生しても、復旧費の調達に困ることのないよう、安定した管理体制を
確立し、マンションの財産価値の長期安定と、居住者間の良好な共同生活環境を
維持して行くためには、「損害保険を活用」していくことが不可欠です。
ほとんどの保険会社で、「マンション総合保険」「マンション管理組合保険」
というような名称で損害保険を販売しています。
マンションの危険
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マンションには、どのような危険があるのでしょうか?
住宅を購入したら火災や地震が心配だから火災保険に加入するという人は
多いと思いますが、考えられる危険はそれだけではありません。
<例えば>
——————————————————————————————————————————————————————————–
1.火事・爆発
2.自然災害(台風・落雷・風水害・雪災・雹災)
3.地震
4.漏水
5.機械設備・共有部分の設備等の事故
6.施設の破損
7.第三者に対する損害賠償事故
8.管理組合対居住者又は居住者同士の損害賠償事故 など
——————————————————————————————————————————————————————————–
どれも気になる事故や災害ですが、第三者が相手になる損害賠償事故
(例えば外壁が崩れて通行人がケガをしたなど)は被害者・加害者の関係に
なる場合があります。
マンションの所在地域によって、台風が多いとか水害の心配はないとか環境は
違います。どんな危険があるかを再確認して必要な補償を考えてください。
保証の範囲
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マンション共用部分専用商品(マンション総合保険等)の補償範囲は
次のとおりです。
——————————————————————————————————————————————————————————–
a. 火災
b. 落雷
c. 破裂・爆発
d. 建物外部からの物体の飛来・衝突
e. 水漏れ
f. 騒じょう・集団行為
g. 風災・ひょう災・雪災(20万円以上)
h. 盗難
i. 水災
j. 臨時費用(上記a~gの事故)
k. 残存物取片付け(上記a~gの事故)
l. 失火見舞金(上記a、cの事故)
m. 地震火災費用
n. 傷害費用(上記a~iの事故)
o. 傷害防止費用((上記a~cの事故)
——————————————————————————————————————————————————————————–
その他に、特約を追加することにより補償される範囲もあります。
保険の種類
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
——————————————————————————————————————————————————————————–
1.火災保険
2.地震保険
3.施設所有者賠償責任保険
4.個人賠償責任保険
5.ガラス保険
6.機械保険
7.これらの保険がセットになっている管理組合専用の保険 など
——————————————————————————————————————————————————————————–
管理組合の保険は上記の1~6がセットになっているイメージです。
どの保険をというよりは、どこの保険会社の管理組合用の保険に加入するかです。
ただし地震保険や個人賠償責任保険特約などの付帯は任意となり、入るか
入らないかの判断も必要となります。