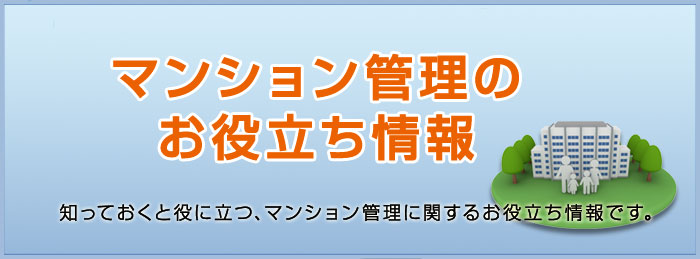議案の説明と議決権
議案の説明
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
総会の2週間前 (標準管理規約第43条) までに発してある招集通知に議案書を
添付してあるので、総会の説明がスムーズにできます。
また、管理会社が説明を行う場合もあります。
▼ 説明が終わると質疑応答です。
—————————————————————————————————————————————————————-
【質問の注意点】
1.会議の目的以外の質問はできません
2.質問者は回答者を指名できません
3.区分所有者のプライバシーに関する質問はできません
4.過去の総会の決議事項に関する質問はできません
【回答の注意点】
1.答えなくてよい質問には議長の判断で回答を拒否できる
2.最も説明に適した回答を指名するのは議長である
3.質問者が納得しなくとも合理的な説明がなされれば回答は終了する
—————————————————————————————————————————————————————-
議決権
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
管理組合の採決方法は、多数決ですが、組合員数と議決権数の両方を数えなく
てはなりません。
議決権とは各区分所有者が持っている議決に当たっての権利のことで、議決権数
とはその数です。
したがって、組合員数と同じではないのです。
標準管理規約第47条では、普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決すると
あります。
管理規約に別段の定めが無い限り、組合員が所有する専有部分の床面積の割合に
よることになります。
つまり、総会議決権総数はマンションの戸数分存在するということです。
議長の権限
議長の権限
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
総会を進めるうえで、議長には総会の秩序を維持し、議事を整理し、
議事の進行を円滑に進めるための「議事整理権」という権限があります。
標準管理規約第42条に「総会の議長は、理事長が務める」とありますが、
議長が単独で判断できることと、できないことがあります。
▼ 議長が単独で判断できること
—————————————————————————————————————————————————————-
1.総会の開会と閉会の宣言
2.質問者や答弁者の指名
3.発言時間の制限
4.議事・議題の審議の順序
5.質疑の打ち切り
6.発言の中止
7.議場の秩序を乱した者の退場
—————————————————————————————————————————————————————-
などがあります。
▼ 議長が単独で判断できないこと
—————————————————————————————————————————————————————-
1.議題・議案に関する修正動議
2.議長不信任の動議
3.総会の延期・続行の動議
—————————————————————————————————————————————————————-
などがあります。
総会は区分所有者が集まって決議を行う合議体なので、議事運営のすべてを
議長の単独判断というわけではないのです。賛否を得たうえで行わなければ
ならない事項もあるのです。
進める順序
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
総会は、議長の開会宣言で始まり、閉会宣言で終わります。
—————————————————————————————————————————————————————-
1.開会のことば
2.理事長のあいさつ
3.議長選出
4.議事録署名人選出
5.議案審議
・第1号議案 活動報告及び収支決算報告
・第2号議案 役員承認
・第3号議案 事業計画の承認
・第4号議案 予算承認
・第5号議案 管理規約の修正と改正
・第6号議案 管理委託契約締結の承認
・その他
6.閉会のことば
—————————————————————————————————————————————————————-
標準的な総会の流れとなります。
招集手続きと議決権
招集手続き
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
標準管理規約第43条で「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の
2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の
日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」と
定めてあります。
招集通知には、総会の日時、場所、議題を記載し、さらに共用部分の変更、
規約の変更、特別決議などの議案内容(議案書)の通知となり区分所有者全員に
発送します。
議題を事前に知ることにより、論議を深めることができますし、出席できない方も
通知された事項について賛否を決定することができます。
議決権
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
標準管理規約第47条では、総会の成立要件を「議決権総数の半数以上を
有する組合員が出席しなければならない。」とし、また、総会の普通決議は、
「出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めてあります。
「会議に参加し、議決に加わる権利」を意味します。
議決権は管理規約によって定めら、原則は、共用部分の共有持分の割合と
なります。
専有部分の床面積の広さによって、その部屋を所有する組合員の一票の権利が
決まります。
出席組合員が、総会成立要件ぎりぎりであった場合、過半数、代理人及び書面に
よる議決権行使も含めての同意が得られれば、決議されることとなります。
議事録には、区分所有者総数、総議決権数、賛否の区分所有者数、議決権数を
記載する必要があります。
総会とは
総会とは
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
管理組合の総会とは、集合住宅の区分所有者によって構成される
最高意思決定機関のことです。
標準管理規約第42条で、「管理組合の総会は、総組合員で組織する。」と
定めてあり、管理組合運営に関して重大な役割を果たします。
業務を執行する理事長・理事・監事等の役員の選任・解任権を持つことが
最高意思決定機関であることを端的に表しています。
例えば、修繕工事の業者選択など意思決定の選択肢を示す場合、多くの
検討事項・交渉事など長期間にかけ綿密に比較検討する作業を、あらかじめ
理事会や修繕委員会などで行い、最終的に総会で業務執行の意思決定の選択肢を、
総会の承認を得ることなどがあります。
総会の種類
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
標準管理規約第42条では、「通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後
2ケ月以内に招集しなければならない。」と定めてあります。
総会には、「通常総会」と「臨時総会」があります。
通常総会は年1回開催され、懸案事項の決議と同時に組合運営の収支決算及び
予算の報告、事業計画ならびに役員の選出などがあります。
臨時総会は、補欠理事の選任や緊急の設備補修工事など急を要する問題が
発生した場合、大規模修繕工事の実施が近づくなど決議しなければならない
内容が増え、定期総会だけでは時間が足りない場合などがあります。
管理費等の収納方式
管理費等の収納方式
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「マンション管理の適正化の推進に関する法律」では管理会社は管理組合の
財産を明確に分別して管理することが義務付けられました。
これを「分別管理」といいます。
「標準管理委託契約書」を改定し、これまでの「収納代行方式」、
「支払一任代行方式」、「原則方式」を廃止して、(イ)、(ロ)、(ハ)の
3つの方式に分かれることとなりました。
▼ (イ)方式
—————————————————————————————————————————————————————-
「収納口座」に管理費等・修繕積立金が収納され、1ヶ月以内に管理費等の
剰余金を「保管口座」(管理組合を名義人とするもの)に移し換える方式です。
—————————————————————————————————————————————————————-
▼ (ロ)方式
—————————————————————————————————————————————————————-
修繕積立金については直接「保管口座」に預入されますが、管理費等については
(イ)方式同様「収納口座」に収納され、1ヶ月以内に管理費等の剰余金が
「保管口座」に移管される方式です。
修繕積立金と管理費等の収納を分けて行うため「口座振替手数料」が2倍かかる
ことになるため、この方式を使うマンションは少ないと思います。
—————————————————————————————————————————————————————-
▼ (ハ)方式
—————————————————————————————————————————————————————-
管理組合の口座は「収納・保管口座」1つだけという方法です。
この方式は、従来の収納代行方式及び支払一任代行方式(収納口座の通帳・印鑑
とも管理会社保管)の場合は、認められません。
—————————————————————————————————————————————————————-
管理会社との付き合い方
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
管理会社に管理業務を任せきりでは、いけないことは言うまでもありません。
しかし、何でも管理会社を根拠もなく疑ってかかることも得策ではありません。
緊張感のある信頼関係を築き良きパートナーであることが一番といえるでしょう。
管理委託契約は、高度な信頼、信用を拠り所とする委任を基礎とし、管理組合の
大事な金銭管理も含まれています。
管理会社は管理のプロのもつ技術を上手に使いつつ、管理組合が主体となり
相互の向上に結び付けたいものです。